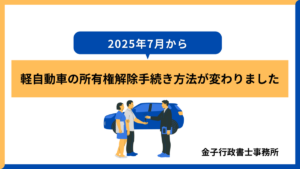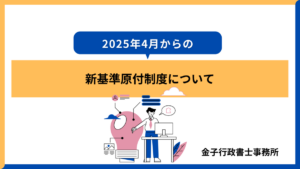「軽二輪」と「小型二輪」の違いについて解説
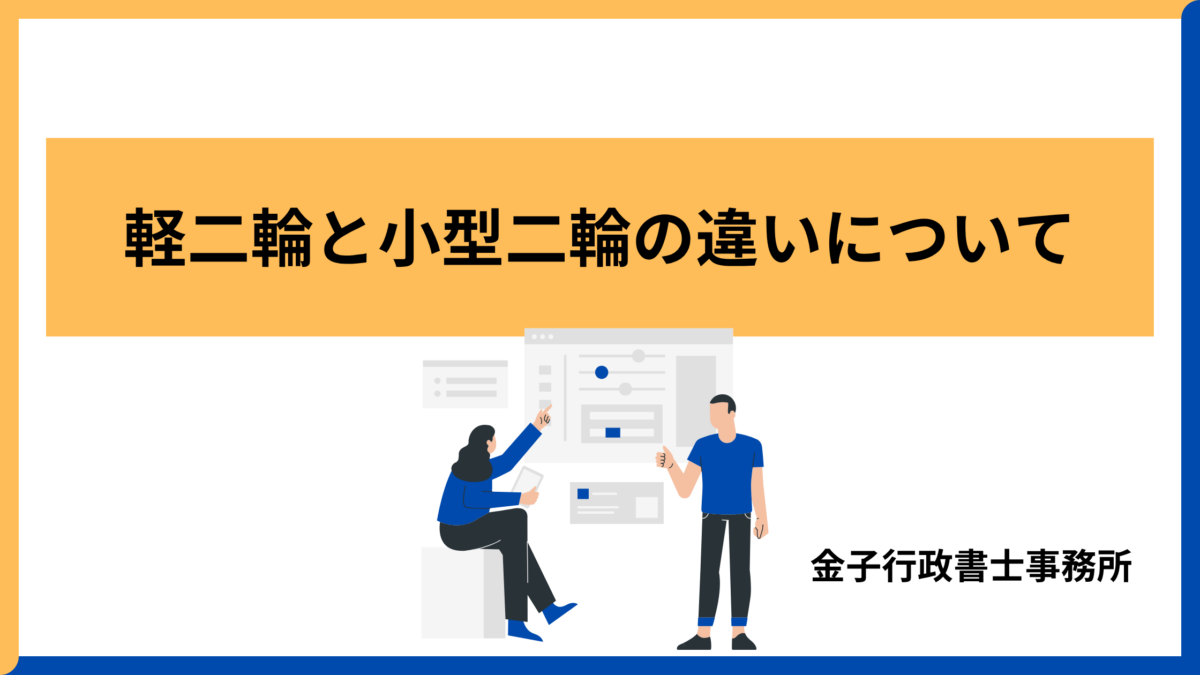
オートバイの購入を検討している方の中には、「軽二輪」と「小型二輪」の違いがよくわからないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
これらの区分は、単に排気量が違うだけでなく、道路運送車両法に基づく手続きや維持費にも違いがあります。
この記事では、「小型二輪」と「軽二輪」の違いを分かりやすく解説します。
軽二輪とは?維持費の手軽さが魅力

軽二輪とは、総排気量が125ccを超え250cc以下のオートバイを指し、道路運送車両法では「二輪の軽自動車(検査対象外軽自動車)」に分類されます。
最大の特長は、車検が不要であることによる維持費の手軽さです。
- 車検(検査)の有無
車検を受ける義務がありません。そのため、車検にかかる費用や手間を省くことができ、維持費を抑えたい方にとって大きなメリットとなります。 - 新規手続きと交付書類
運輸支局で行う手続きは「新規届出」となり、車両を持ち込む必要はありません。手続きが完了すると、「軽自動車届出済証」が交付されます。
小型二輪とは?パワフルな走りが魅力

小型二輪とは、総排気量が250ccを超えるオートバイのことで、道路運送車両法では「二輪の小型自動車」に分類されます。
パワフルなエンジンによる高い走行性能が魅力ですが、車検が義務付けられている点が軽二輪との大きな違いです。
- 車検(検査)の有無
新車登録から3年後、以降は2年ごとに車検(検査)を受ける必要があります。車両が国の保安基準に適合しているか定期的にチェックするため、安全性が保たれやすい反面、維持費と手間がかかります。 - 新規手続きと交付書類
運輸支局で「新規登録(検査)」を行います。車両が保安基準を満たしていることを証明する必要があり、合格すると「自動車検査証(車検証)」が交付されます。
軽二輪と小型二輪の違いを一覧で比較
軽二輪と小型二輪の主な違いを以下の表にまとめました。
| 比較項目 | 軽二輪 | 小型二輪 |
|---|---|---|
| 排気量 | 126cc ~ 250cc | 251cc 以上 |
| 車検 | 不要 | 必要 (初回3年、 以降2年ごと) |
| 手続きの場所 | 運輸支局 | 運輸支局 |
| 行政上の手続き | 運輸支局での 「届出」 | 運輸支局での 「検査」 |
| 交付される書類 | 軽自動車届出済証 | 自動車検査証 (車検証) |
| 税金の種類 | 軽自動車税 | 軽自動車税 |
| ナンバープレートの色 | 白地に緑文字 (枠なし) | 白地に緑文字 (緑枠あり) |
まとめ:あなたに合うのはどっち?軽二輪と小型二輪の選び方
軽二輪と小型二輪の選択は、ライフスタイルや重視するポイントによって異なります。
軽二輪はこんな方におすすめ
- 維持費をできるだけ抑えたい方
- 車検の手間を省きたい方
- 通勤や街乗りなど日常の足として手軽に使いたい方
小型二輪はこんな方におすすめ
- 高速道路を使ったツーリングなど、長距離走行を楽しみたい方
- パワフルで高い走行性能を求めたい方
忘れてはいけない共通点
どちらの区分も、自賠責保険への加入は法律で義務付けられています。
バイクを選ぶ際は、それぞれのメリット・デメリットをよく理解し、ご自身の使い方に最適な一台を見つけましょう。
自賠責保険料一覧はこちら>>
⇒軽二輪はコンビニで自賠責保険の加入手続が可能です。
岩手県での軽二輪・小型二輪の各種手続は金子行政書士事務所にお任せください。
当事務所では、岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)の軽二輪・小型二輪の各種手続きの代行を承っております。
全国の二輪販売店様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
▼法令はこちら
道路運送車両法第97条の3
(検査対象外軽自動車の使用の届出等)
第九十七条の三 検査対象外軽自動車は、その使用者が、その使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に届け出て、車両番号の指定を受けなければ、これを運行の用に供してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法施行規則第35条の2
(検査対象外軽自動車)
第三十五条の二 法第五十八条第一項の国土交通省令で定める軽自動車は、次の各号に掲げる軽自動車とする。
一 二輪の軽自動車←軽二輪
二 カタピラ及びそりを有する軽自動車
三 被牽けん引自動車である軽自動車(第一号に掲げる軽自動車又は小型特殊自動車により牽けん引されるものに限る。)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)