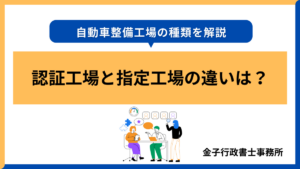車検と予備検査の違いは?予備検査の種類やメリットも解説
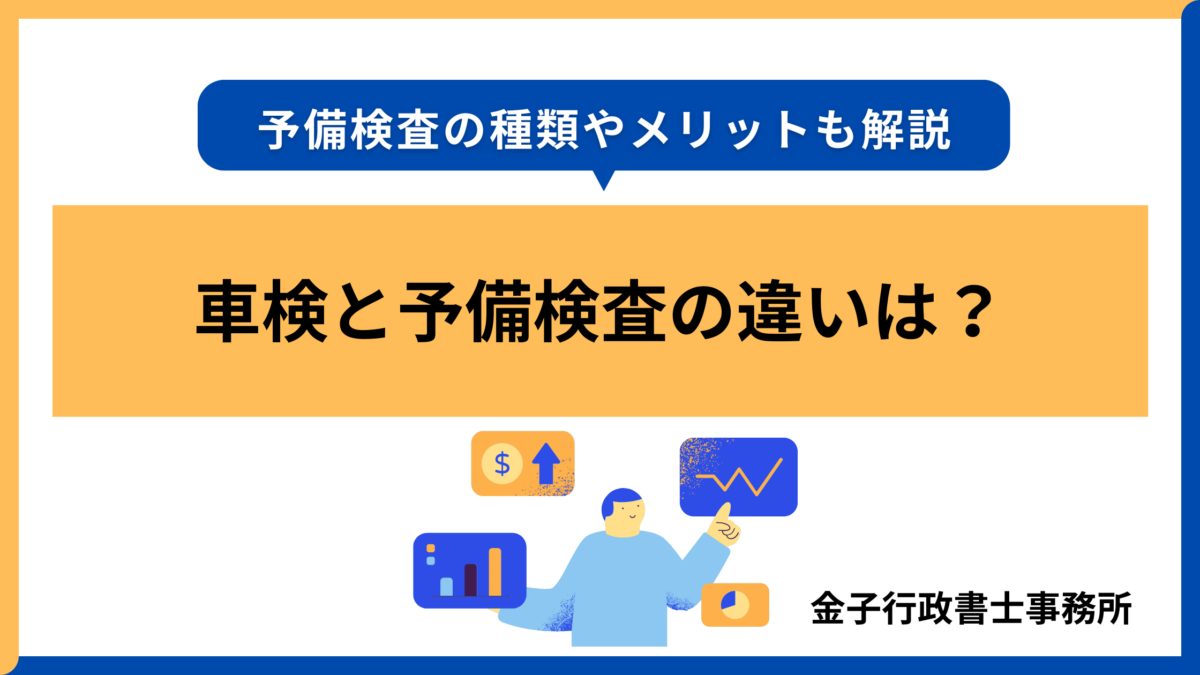
車検と予備検査の違い、ご存じですか?車検は多くの方が経験する手続きですが、「予備検査」という言葉は、あまり聞きなじみがないかもしれません。
実は、予備検査には2種類あり、それぞれ目的や手続きが異なります。
この記事では、車検と予備検査の違いを分かりやすく解説し、予備検査の種類やメリットについても詳しくご紹介します。
車検とは?その目的と特徴を解説
車検とは、車両が道路運送車両法で定められた保安基準に適合しているかを確認するための検査です。
一般的な乗用車の場合、新車登録から3年後、その後は2年ごとに受けることが義務付けられています。
車検に合格すると、自動車検査証(車検証)と検査標章(ステッカー)が交付され、公道を走行できるようになります。
車検の主な特徴
- 検査場所
・運輸支局や軽自動車検査協会、または指定工場(民間車検場) - 合格後の証明書
・車検証(自動車検査証) - 有効期間
・2年間(新車は3年間)※一般的な乗用車の場合 - 法定点検
・一般的に車検と併せて行われる
予備検査とは?車検との違いを解説
予備検査は、車検とは異なり、ナンバープレートのない車やユーザー車検を受ける前の車両に対して行われる検査です。
車両登録の前に予備検査に合格しても車検証は発行されず、「自動車予備検査証」が交付されます。この証明書の有効期間は3か月で、期間内に車両登録を行う必要があります。
予備検査には2種類ある!それぞれの目的と特徴
予備検査には以下の2種類があります。それぞれの目的や特徴を理解しておきましょう。
①ナンバープレートのない車の予備検査
ナンバープレートがない車両(一時抹消登録された車など)に対して行われる検査です。
この検査に合格すると「自動車予備検査証」が交付され、車両登録を行うことで再び公道を走行できるようになります。
特徴
- 検査場所
・運輸支局等 - 合格後の証明書
・自動車予備検査証 - 有効期間
・3か月 - 法定点検
・別途実施が必要 - 車検が切れた車や抹消登録された車が対象
- 車両登録のために行われる手続き
- ナンバープレートは発行されない
②ユーザー車検前の予備検査
ユーザー車検をスムーズに通過するための事前チェックとして行う任意の検査です。
車両の状態を確認し、車検本番での不合格リスクを減らし、必要な整備箇所を把握することができます。
特徴
- ユーザー車検を受ける人が任意で行う検査
- 車検本番の不合格リスクを軽減
- 民間が運営する予備検査場(テスター屋とも呼ばれる)で実施可能
↑運輸支局の近くにあることが多い
車検と予備検査の比較表
| 項目 | 車検 | 予備検査 |
|---|---|---|
| 目的 | 車両の保安基準適合 確認 | 車両登録やユーザー車 検準備 |
| 対象車両 | 有効な車検証が交付 されている車両 | ナンバープレートのな い車両、ユーザー車検 前の車両 |
| 合格後の証明書 | 自動車検査証 (車検証) | 自動車予備検査証※1 |
| 有効期間 | 2年(新車は3年)※2 | 3か月 |
| 法定点検 | 含まれる | 含まれない |
※1 ナンバープレートのない車両の場合
※2 一般的な乗用車の場合
予備検査を受けるメリット
予備検査を受けることで、以下のようなメリットがあります。
ナンバープレートのない車の予備検査の場合
車検切れの車両を購入する場合、予備検査済みであれば、購入後に車検を受ける必要がなく、登録手続きをスムーズに進めることができます。
特に中古車オークションや個人間取引での車両売買時には、予備検査証が付いている車両(予備検査付き、予備検査渡し)であれば安心して取引を行うことができます。
ユーザー車検前の予備検査の場合
車検で不合格となり再検査が必要になるリスクを軽減することができます。車検当日に不備が見つかると、修理や再検査のために余計な時間と費用がかかります。
予備検査を受けることで、これらの手間を事前に防ぐことができます。
まとめ
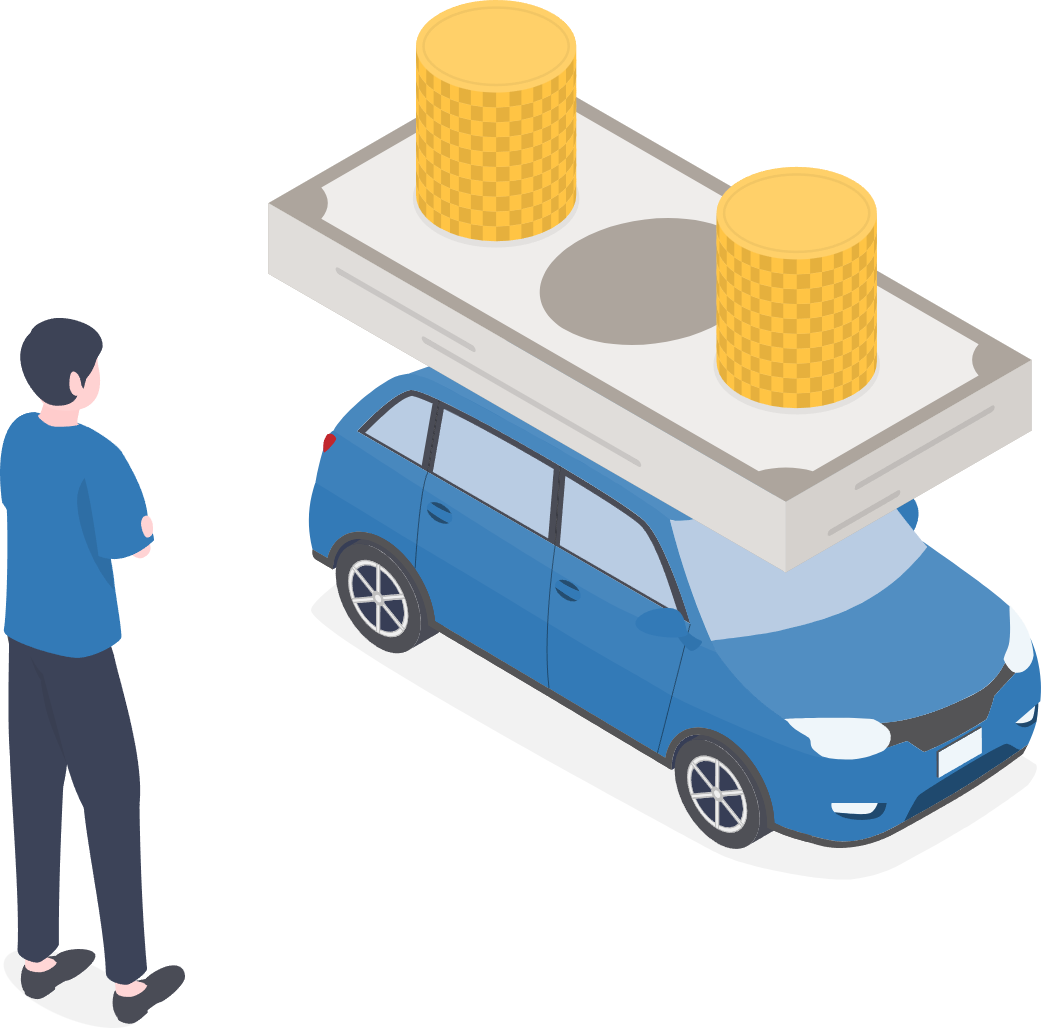
車検と予備検査は、似ているようで実は目的も手続きも大きく異なります。車検は、車が公道を安全に走行できる状態かどうかを確認するための、法律で義務付けられた検査です。
一方、予備検査は、ナンバープレートがない車や、ユーザー車検を受ける前に任意で行う検査です。
特に、予備検査には2つの種類があり、それぞれ目的と特徴が異なるため、しっかりと理解しておくことが重要です。
盛岡の車庫証明、岩手県内の自動車・バイク登録は金子行政書士事務所にお任せください!
金子行政書士事務所では車庫証明・自動車登録・バイク(小型二輪・軽二輪)登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
車庫証明は盛岡市を中心に、自動車登録は岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)に対応しております。
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
道路運送車両法第71条
(予備検査)
第七十一条 登録を受けていない第四条に規定する自動車又は車両番号の指定を受けていない検査対象軽自動車若しくは二輪の小型自動車の所有者は、当該自動車を提示して、国土交通大臣の行う予備検査を受けることができる。
2 国土交通大臣は、予備検査の結果、当該自動車が保安基準に適合すると認めるときは、自動車予備検査証を当該自動車の所有者に交付しなければならない。
3 自動車予備検査証の有効期間は、三月とする。
4 自動車予備検査証の交付を受けた自動車についてその使用の本拠の位置が定められたときは、その使用者は、国土交通大臣に当該自動車予備検査証を提出して、自動車検査証の交付を受けることができる。
(以下略)
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)