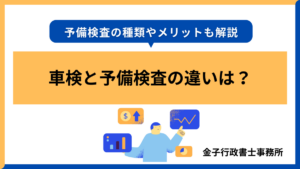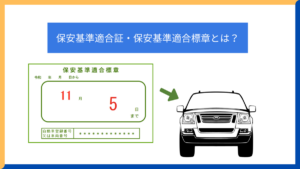認証工場と指定工場の違いは?自動車整備工場の種類を解説
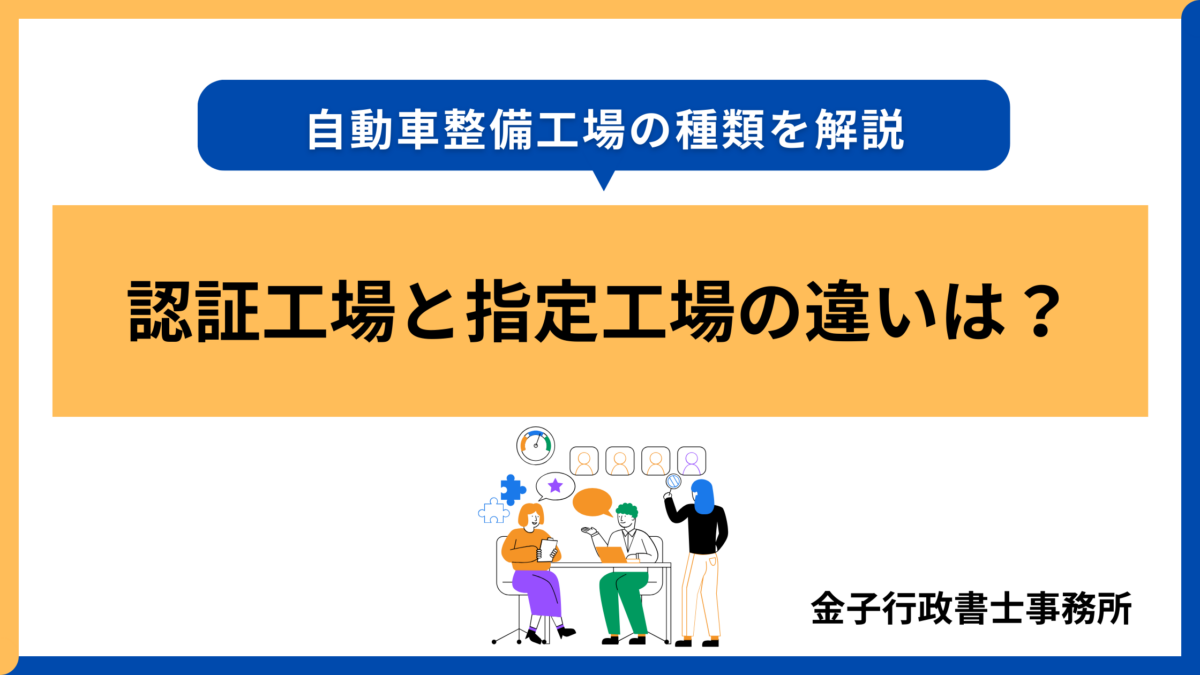
愛車の車検や整備を依頼する際、どの自動車整備工場を選べばよいか迷ったことはありませんか?整備工場には「認証工場」と「指定工場」の2種類があり、それぞれ特徴や提供サービスが異なります。
この記事では、認証工場と指定工場の違いをわかりやすく解説し、あなたに最適な整備工場を選ぶためのポイントをご紹介します。
自動車整備工場の2つのタイプ
日本の自動車整備工場は、道路運送車両法に基づき大きく「認証工場」と「指定工場」の2つに分類されます。それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
認証工場とは
認証工場とは、道路運送車両法第78条第1項に基づき、地方運輸局長から「認証」を受けた整備工場で、安全な整備を提供するための基準を満たしており、車両の分解整備を行うことができます。
認証工場の主な特徴は以下の通りです。
- 分解整備の実施が可能
・エンジンやブレーキなど安全に関わる重要部品の分解整備ができます。 - 施設・人員基準
・一定規模の作業場と作業機械、必要な資格を持つ整備士を配置しています。 - 車検の流れ
・整備後、運輸支局等に車両を持ち込んで検査を受ける必要があります。 - 標識の掲示
・認証工場であることを示す標識を提示しています。
指定工場とは
指定工場は、認証工場の中でもさらに厳しい基準を満たし、道路運送車両法第94条の2第1項に基づき、地方運輸局長から「指定自動車整備事業」の「指定」を受けた整備工場です。一般的には「民間車検場」とも呼ばれています。
指定工場の主な特徴は以下の通りです。
- 自社での車検が完結
・自社内で車検のすべての工程を完了できます。 - 設備・技術・組織
・認証工場の基準に加え、検査設備や自動車検査員の配置など、より高い基準を満たしています。 - 保安基準適合証の発行
・自動車検査員による検査後、保安基準適合証を発行でき、これにより運輸支局などへ車両を持ち込む必要がありません。 - 標識の提示
・指定工場であることを示す標識を掲示しています。
保安基準適合証・保安基準適合標章とは?必要な場面と役割について解説>>
認証工場と指定工場の比較表
| 項目 | 認証工場 | 指定工場 |
|---|---|---|
| 車検の実施 | 車検場への車両の 持ち込みが必要 | 工場内で完結可能 (保安基準適合証の 発行が可能) |
| 設備・人員 | 一定規模の作業場、 作業機械、分解整備 に従事する従業員 | 認証工場の基準 +検査設備、自動車 検査員、管理組織 |
| 対応範囲 | 点検・整備 (車検は運輸支局 への持ち込みが必要) | 点検・整備から 車検まで一貫対応可能 |
整備工場選びのポイント
車検を依頼する際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 工場の種類の確認
・認証工場か指定工場かを確認する。 - 標識の確認
・標識が掲示されているか確認する。 - 整備内容の確認
・分解整備を含む点検・整備内容を確認する。
まとめ

自動車整備工場には「認証工場」と「指定工場」の2種類があり、それぞれ異なる特徴を持っています。車検や整備を依頼する際は、ご自身のニーズや優先事項を考慮して、適切な整備工場を選択しましょう。
また、工場選びの際は、必ず認可を受けた工場(認証工場または指定工場)であることを確認し、安全で適切な整備を受けるようにしましょう。
盛岡の車庫証明、岩手県内の自動車・バイク登録は金子行政書士事務所にお任せください!
金子行政書士事務所では車庫証明・自動車登録・バイク(小型二輪・軽二輪)登録など、車両関連手続きを中心に業務を承っております。
車庫証明は盛岡市を中心に、自動車登録は岩手県内全域(岩手・盛岡・平泉ナンバー)に対応しております。
全国のカーディーラー様、自動車販売店様、行政書士事務所様、個人のお客様からのご依頼をお待ちしております。
▼法令はこちら
道路運送車両法第94条の5第1項
(保安基準適合証等)
第九十四条の五 指定自動車整備事業者は、自動車(検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をした場合において、当該自動車が保安基準に適合する旨を自動車検査員が証明したときは、請求により、保安基準適合証及び保安基準適合標章(第十六条第一項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車並びに第六十九条第四項の規定による自動車検査証返納証明書の交付を受けた検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあつては、保安基準適合証)を依頼者に交付しなければならない。ただし、第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき自動車については、臨時検査を受けていなければ、これらを交付してはならない。
(略)
11 第一項の規定による自動車検査員の証明を受けた自動車が国土交通省令で定めるところにより当該証明に係る有効な保安基準適合標章を表示しているときは、第五十八条第一項及び第六十六条第一項の規定は、当該自動車について適用しない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第58条第1項
(自動車の検査及び自動車検査証)
第五十八条 自動車(国土交通省令で定める軽自動車(以下「検査対象外軽自動車」という。)及び小型特殊自動車を除く。以下この章において同じ。)は、この章に定めるところにより、国土交通大臣の行う検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けているものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
道路運送車両法第66条第1項
(自動車検査証の備付け等)
第六十六条 自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)